“Be yourself. No one can say you’re doing it wrong.”
(自分らしくいればいい。誰も君が間違っているなんて言えないさ。)
人生においては、この言葉通り「自分らしく」あることが正解かもしれません。
しかし、登記の手続きにおいて「自分らしく(英語のまま)」書類を提出すると、法務局から即座に「訳文をつけてください!」と補正を食らってしまいます。
相続登記や渉外登記では、英語などの外国語で書かれた書類(特別受益証明書や宣誓供述書など)を添付する際、必ず「日本語の訳文」を付けなければなりません。
今回は、意外と知られていない「訳文の作成ルール」について解説します。
疑問:翻訳は「誰」が「どうやって」やるの?
「翻訳なんて頼んだら高いんじゃないの?」
「翻訳家の資格証明書とかいるの?」
ご安心ください。日本の登記実務における翻訳ルールは、意外とシンプル(寛容)です。
Q1. 翻訳するのに「資格」は必要ですか?
A. 不要です。一般の方でOKです。
国家資格を持つ翻訳家である必要はありません。英語が得意なご親族や、依頼を受けた司法書士、あるいはご自身(申請人)が翻訳しても全く問題ありません。
(※ただし、ブラジルのように法定翻訳人の制度があり、その資格者でなければ公文書として扱われない国も一部ありますが、日本の登記所に提出する分には基本的に誰でも構いません。)
Q2. 翻訳者の「印鑑証明書」は必要ですか?
A. 不要です。
翻訳の内容が正しいことを担保するために、翻訳者の実印や印鑑証明書までは求められていません。認印(または職印)で大丈夫です。
Q3. 最後に「何」を書けばいいですか?
A. 「これは訳文です」という旨と、「署名(または記名)・押印」があればOKです。
実践:訳文の末尾の書き方(奥書)
翻訳した書類の最後には、その責任の所在を明らかにするため、以下のように記載してハンコを押します。
記載例
「以上、翻訳いたしました。」
(または「上記は、原文書の正確な翻訳です。」など)
翻訳者 法務 太郎 ㊞
誰の名前を書く?(申請人 vs 翻訳者)
実務書や古い先例(登記研究149号など)では、「申請人(登記権利者・義務者)」が訳文である旨を記載すべき、とされることもあります。
しかし、現在の実務や専門書(『渉外不動産登記の法律と実務』山北英仁著 P92など)では、実際に翻訳した人が記名押印すれば足りるとされています。
したがって、司法書士が翻訳した場合は司法書士名で、本人が訳した場合は本人名で記載すれば問題ありません。
サイン? それとも記名押印?
古い先例(登記研究161号)には「署名・押印」と書かれていますが、現在の実務では「記名・押印(パソコン入力+ハンコ)」で処理しても補正になることはありません。
根拠となる先例・資料
心配性な方(あるいは法務局との協議用)のために、根拠資料を挙げておきます。
- 登記研究161号「訳文者は一般人で差し支えない」「登記権利者及び登記義務者において、訳文である旨を記載し、署名、押印するのが相当」
- 登記研究149号「翻訳者の署名等は不要だが、申請人が『右は訳文である』旨の記載をする」
- 登記研究213号「登記申請代理人(司法書士)の作成したもので差し支えない」
- 『渉外不動産登記の法律と実務』(山北英仁 著)P92「翻訳した後末尾に『上記翻訳しました』旨記載し記名押印すればよい」
まとめ
外国語の書類が出てきても、身構える必要はありません。
- 翻訳者に資格はいらない。
- 印鑑証明もいらない。
- 「翻訳しました」と書いてハンコを押せばOK。
「自分らしく」翻訳をして、堂々と提出しましょう!(もちろん、誤訳には気をつけてくださいね)
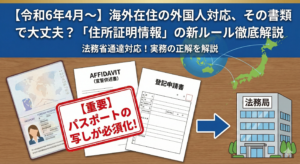
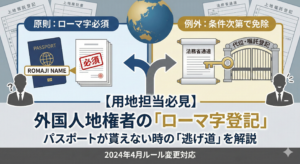






コメント